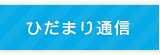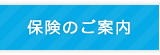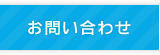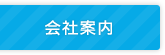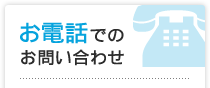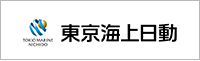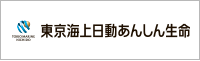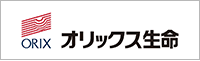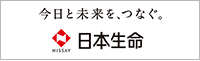———————————————————————-
“師も走るほど忙しい”12月からお正月にかけては、イベントも多く何かと慌しいもの。
長丁場の忙しさを元気に乗り切るために、今年は冬至にひと息つきませんか?
———————————————————————-
【そもそも冬至とは?】
冬至とは、北半球において一年で最も昼間が短く、夜が長い日です。
太陽の高さも最も低くなり、日差しが弱くなります。今年の冬至は12月22日で、東京では日の出が6時47分頃、日の入りが16時32分頃と予測されています。夏至と比べると、日照時間はおよそ5時間近く(東京の場合)も短くなります。
一年で最も日が短いということは、翌日からは日が長くなっていくということ。そのため、昔の人は冬至を“太陽が生まれ変わる日”と考え、世界各地でお祝いをしていたそうです。
中国や日本では、一陽来復(いちようらいふく)といい、冬至を境に運が上昇すると考えました。
【冬至に食べると縁起がよいもの】
ほかの季節行事と違わず、冬至にも、この日に食べるとよいといわれる行事食がいくつかあります。
☆かぼちゃ
一年で最も日が短く寒いとされた冬至に、ビタミンEやカロチンなど栄養豊富なかぼちゃを食べることで、無病息災を願ったといわれています。本来夏が旬のかぼちゃを長期保存をして冬に備えた、生活の知恵でもあります。
かぼちゃを小豆と一緒に煮る“いとこ煮”などを頂きます。小豆も冬至の食べ物で、小豆の赤色は邪気をはらう力があると考えられています。
☆「ん」がつくもの
“運盛り”といって、なんきん(かぼちゃ)、にんじん、れんこん、うどん、だいこん、ぎんなん…など、「ん」がつくものは縁起がよく、これらを冬至に食べると、運が呼び込めるといわれています。
☆冬至粥
冬至粥とは、小豆入りのお粥のこと。
邪気をはらい、翌日から運気を呼び込むために食べます。
☆こんにゃく
地方によっては、冬至にこんにゃくを食べます。
“砂おろし”といい、こんにゃくを食べることで、体内にたまった砂を排出するとされています。
【ゆず湯で体もポカポカに】
冬至の習慣としてもうひとつ挙げられるのが、ゆず湯。冬至=湯治、ゆず=融通が利くの語呂合わせともいわれていますが、冬至にゆず湯につかると、「一年中風邪をひかない」との言い伝えもあります。実際に、冬に旬を迎えるゆずには、血行を促進して冷えや痛みを緩和する効果もあり、理にかなっているのです。
ゆず湯の方法はいくつかありますが、ゆずの香りや成分をより楽しみたいのであれば、輪切りや半分にカットしてお風呂に浮かべるのがベストです。最低でもゆずを5〜6個は使いたいもの。種や果肉が浴槽に残り掃除が面倒ならば、風情にはやや欠けますが、洗濯ネットや生ゴミ用のネットを利用すると楽チンです。
体を温めるだけでなく、さわやかな香りでリラックス効果も期待できるゆず湯は、寒い冬を元気に過ごすための先人の知恵でもあります。
———————————————————————-
冬至は、クリスマスやお正月のように華やかなイベントではありませんが、いにしえから伝わる、冬の生活を楽しむ粋なひとときといえるのではないでしょうか。
———————————————————————-